デジタルって何?
−デジタル社会で生きぬくために−
2.2 EC
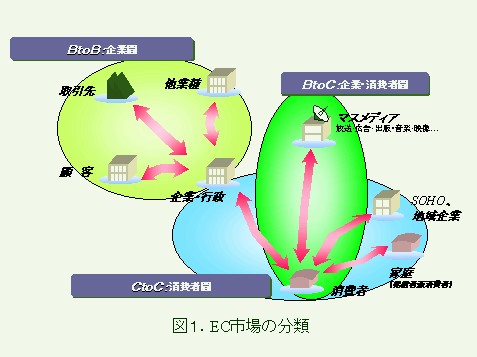
インタネットを基盤として商売することを電子商取引、 Electric
Commerce と呼びます。一昔前はネットワークを介して電子的に商売することと認識されていましたが、そのネットワークがインタネットを利用するのが当たり前になりました。最近は単に頭文字を使って
Eコマースと呼んだり、インタネットを利用する商売なのでIコマースと呼んだりします。企業と企業との間での商売を
BtoB(Business to Business)、企業と消費者との間での商売をBtoC(Business to
Consumer)と分類されますが、デジタル社会になるとCtoC(Consumer to Consumer)という新しい市場も登場してきます。
例えば、消費者が不要になったものを自分のホームページ上で必要とする人に譲る商売です。今はなかなか消費者自らが手がけるほどインタネットはこなれていないので、仲介業者が利用者の手伝いをしながら商売を進めています。インタネットを使ったオークションなどはBtoC
の一例といえますが、消費者自身が少し賢くなるとCtoC として新しいビジネスモデルにシフトしていくものと思われます。
ECについては多くの本でわかりやすく紹介されているので、ここでは視点を変えて、社会構造がどうパラダイムシフトしていくのか考えてみたいと思います。広島を拠点とする家電量販店「ダイイチ」がインタネットを使った洋書販売を日本で6年程前に手がけ、ECの先駆的な事例として話題になりました。洋書を紀伊国屋や三省堂で購入するより期間が短く、購入金額も安い。広島大学では先生や学生がリピータ(口コミ)となり取り扱い量も急増しました。1億円の売上を達成するには2億円の初期投資が必要といわれていた当時の常識を覆し、数千万円の初期投資と、スタッフ数名でスタート。店舗不要、在庫なし、低コスト、時間場所を問わず、流通機能をアウトソースするなど、昨今話題になっているサプライチェーンマネジメントを先駆けました。
大手流通業界には既得権がはびこり、非効率的な事業構造があってもそれを変えられなかったのです。ECはそうしたビジネスの矛盾点を見つけ、それを正して商売することといえます。
ダイイチの例はBtoC の場合ですが、BtoB についても大手企業が関連業界との仕事の進め方にデジタル技術を積極的に導入を図り、
EDI(Electric Data Interchange)を実現してきているという多数の例があります。
両社に共通することは矛盾だらけの既得権をどう打破していくか、ということができます。また、これから登場するであろうCtoC
の世界では、だれもがいつでも手軽に商売できるということです。 家内は一昨年10月にボランティア活動のためにホームページを立ち上げました。これはよくある宣伝活動でしかありませんが、これを基盤に商売に展開することはいつでも可能になるわけです。ホームページの性格からすると日用品交換の場の提供が考えられますが、今のところ本人はそれに気づいていないと思います。いずれそうしたECをやり始めるかもしれません。
(続く)
|